本記事は「情弱の解剖学」の書評記事です。
「情弱」
この言葉を聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?インターネットに疎い人?デマに振り回される人?──実はその裏には、もっと深く根本的な“感情の脆弱さ”も隠れています。
本書『情弱の解剖学』では、単なる情報リテラシーの欠如では語りきれない「情弱」の本質を明らかにしています。ポイントは、“情弱”には2つの意味があるということ。一つは外的な情報に対する脆さ、もう一つは自分の思考力や判断力、感情対する内的な弱さです。
この本を読んで感じたのは、情弱は決して一部の人だけの問題ではないということです。SNSやネット広告、フェイクニュースがあふれる現代において、誰もが“情弱”になりうる。だからこそ、正しい理解と「治し方」が求められるのです。
こんな人におすすめ
・SNSやネットニュースに振り回されがちだと感じている方
・怒りや不安といった感情に振り回され、やりたいことをできていない方。
・情報社会における「自分の在り方」を見直したいと考えている方。
・情弱になりたくない、情弱から脱したい方。
基本情報・あらすじ
基本情報
作者について
…..ごめんなさい。正直本書を読むまでは胡散臭い人なんだろうなと思っていました….
しかし本書の内容はとてもためになるものでした!!
あらすじ
この本との出会いは
「なんで私やあの人は簡単に騙されてしまうんだろう?」
──そんな疑問が、私がこの本に興味を持ったきっかけでした。SNSでデマに踊らされる人、怪しい副業に手を出す人、根拠のない健康法にのめり込む人……身の回りに“情弱”と思える場面があふれていたのです。
ちょうどその時、Kindleのおすすめ欄で見つけたのが『情弱の解剖学』でした。「情弱」という言葉はネットスラングとして広く使われていますが、それを「解剖学」と結びつけて学問的に分析するというタイトルのギャップに、強く惹かれました。
実際に読んでみると、情報リテラシーの話だけでなく、感情面の脆さにも踏み込んでおり、自分自身にも当てはまる部分が多くありました。タイトルのユニークさに惹かれて手に取った本が、思わぬ深い気づきを与えてくれたのです。
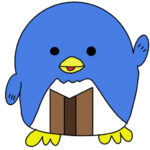 でぱーちゃー
でぱーちゃー情弱乙wwwwとかで使われるネット用語のイメージが強かったです(笑)
感想・学んだこと
現代社会だからこその、2つの情弱を理解する
「自分は情弱なんかじゃない」
そう思った時点で、もうその罠に片足を突っ込んでいるかもしれません。なぜなら、現代社会において“情弱”とは、単なるネットリテラシーの低さだけではなく、「感情」と「情報」の2つの側面から静かに私たちを蝕んでいるからです。
本書では、情報に対する無知や盲信と、感情の暴走や制御不能という、まったく異なる2つの“脆さ”を「情弱」として定義しています。特に現代は情報が洪水のように流れ、同時に感情もSNSなどを通して揺さぶられる場面が多くなっています。この2つの情弱は、知らない間に私たちの思考や行動を縛り、自立した判断力を奪っていきます。
私自身もまさにその例に当てはまる経験をしたことがあります。それは「タイヤ交換」です。命に関わる部分だからと、私は毎年お店に頼んで1万円近い費用を払っていました。しかしあるとき「本当に自分でできないのか?」と疑問に思い、ネットで調べてみたところ、ジャッキとレンチさえあれば誰でも簡単に交換できることを知りました。最初は「危ない」「失敗したらどうしよう」といった感情に足を引っ張られましたが、実際にやってみると驚くほど簡単。今では家族全員の車も含めて、自分で交換しており、年間で3万円以上の節約になっています。
この体験を通じて痛感したのは、「知らないこと」と「怖いからやらないこと」のどちらもが“情弱”の根本にあるということです。情報を得ようとしなかった自分、そして不安に勝てなかった自分──その両方を認識することで初めて、改善のスタートラインに立てました。
情弱から抜け出す第一歩は、「自分は大丈夫」という思い込みを捨てることです。そうすれば、自分の中の“見えない弱さ”にも気づくことができるようになります。現代を生き抜くには、まずその自覚が何よりも大切なのだと学べました。
情弱の治し方は自己規律にあり
私たちはしばしば、「知っているのにできない」「わかっているのに動けない」という葛藤に悩まされます。その背景には、感情に流されて行動できない“感情面の情弱”と、情報収集を怠る“情報面の情弱”の二重構造が潜んでいます。そしてこの2つの情弱を克服する鍵が、「自己規律」だと本書では説明されています。
感情面での情弱は、怖い・面倒・不安といった“気持ち”に支配されて行動を止めてしまう傾向があります。こうした感情は誰しも抱えるものですが、それを乗り越えるには「小さな成功体験」と「継続」が必要です。
たとえば私自身、ダイエットに取り組んだ際、最初は「きつい筋トレ」や「糖質制限」など過激な方法ばかりを試しては挫折していました。ですが、あるとき思い切って「散歩」から始めることにしました。たった15分でも歩けた日には「今日はやれた」と思えたのです。そうした“自分との小さな約束”を守り続けた結果、30㎏の減量に成功しました。自己規律とは、自分を甘やかさず、小さな達成感を積み重ねる力なのだと実感しています。
一方で、情報面の情弱は「知らないことを放置する」「これで十分と思い込む」ことから始まります。時代の流れが速い今、5年前の常識がもう通用しないことも珍しくありません。だからこそ、私たちは常に学び続ける姿勢が必要です。私がそれを強く意識したのは、NISAを学び始めたときでした。以前は銀行預金だけで資産を管理していましたが、少しずつ「お金にも働いてもらう」という考えに切り替えるため、投資の勉強を始めました。初めは何が何だか分からず戸惑いましたが、少しずつ理解が深まると、NISAを活用した積立投資にも前向きになれました。
ここで大切なのは、完璧を目指さないことです。感情も情報も、一度にすべてをコントロールするのは不可能です。しかし、“少しでも前に進もうとする姿勢”こそが、情弱を脱却する唯一の方法です。小さくてもいい、自分を律し、学び続けること──それが私たちを不安や無知から解放してくれます。
この小さくても成功体験を重ねるという点は、以前ご紹介した「ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣」に似たことが紹介されていました。世界的名著にも紹介されている要素、重要じゃないはずありません。
以前の記事は↓からどうぞ!
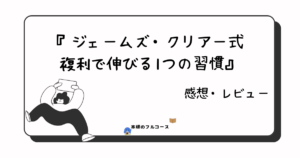
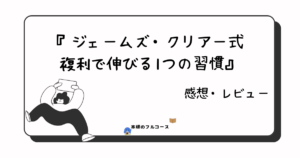
結局のところ、「情弱」は誰の中にもあります。だからこそ、自己規律という内なる力を育てながら、情報と感情に振り回されない強さを身につける必要があるのです。
本書はこのような学びを優しい文体で説明してくれました。自分の生き方を考え直す機会をくれる素敵な本でした。
まとめ
今回は書籍、「情弱の解剖学 人はなぜ弱者化し、どうすれば抜け出せるのか?」についてのl¥感想・レビューでした。
『情弱の解剖学』は、私たちが見過ごしがちな「情報」と「感情」の弱さに光を当て、それをどう克服するかを丁寧に教えてくれる一冊です。
自分は大丈夫と思っている人こそ、気づかぬうちに情弱になっているかもしれません。本書を通じて自分を見直し、一歩前に踏み出すヒントを得てください。ぜひ読んでみてほしいです。
↓から各ストアへのリンクもあります。ご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。良かったらXのフォローもよろしくお願いします。
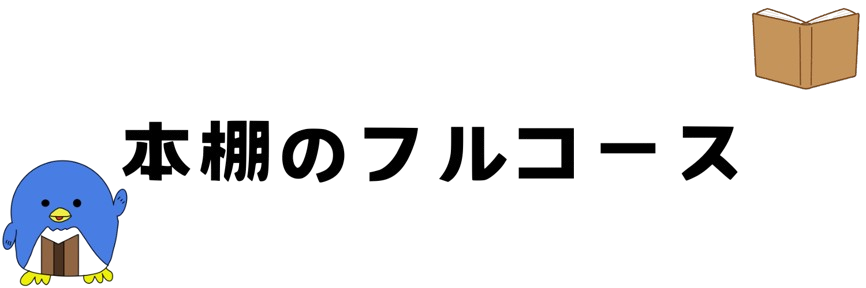
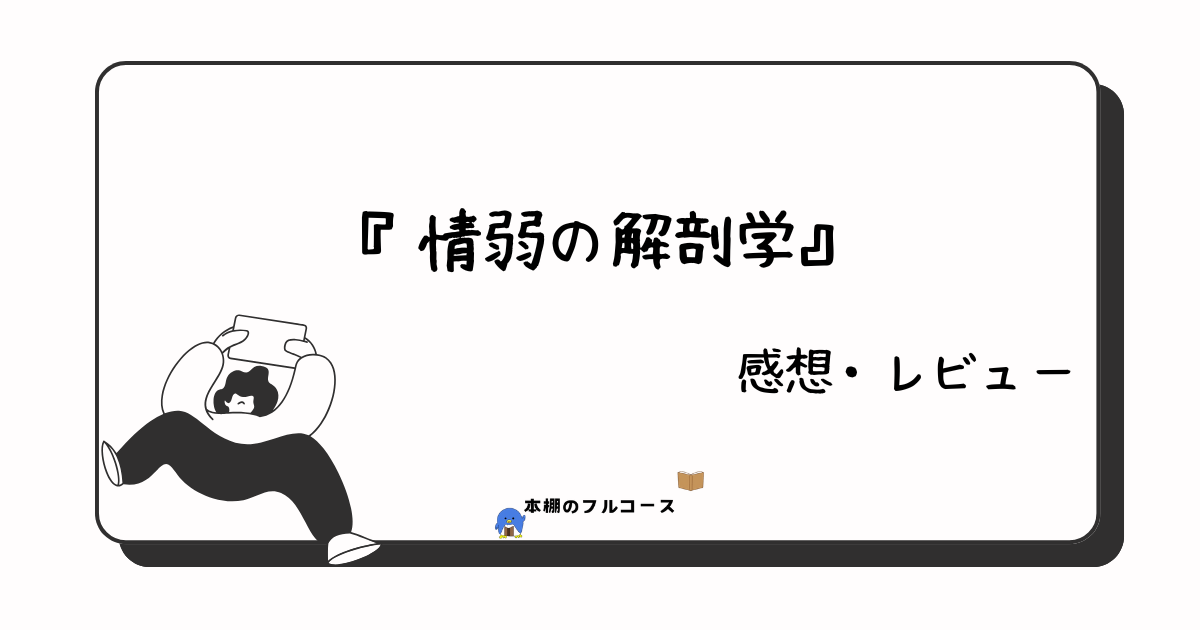
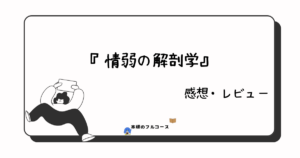
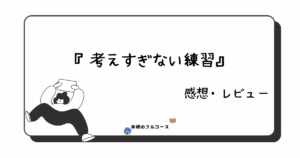

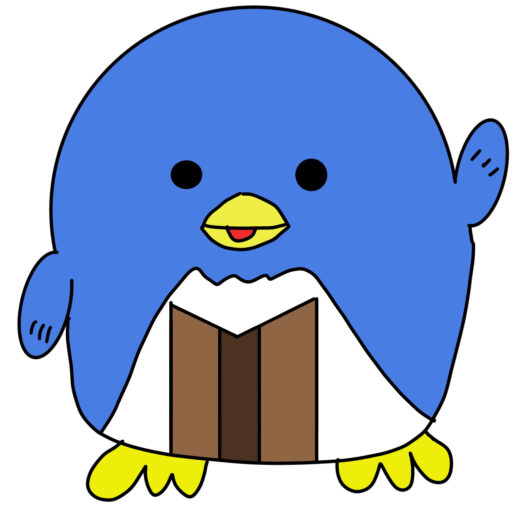
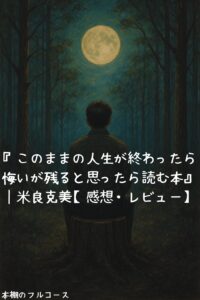
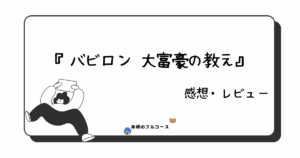
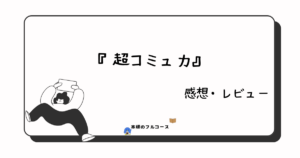
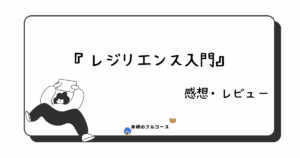
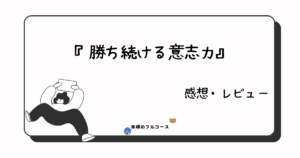
コメント